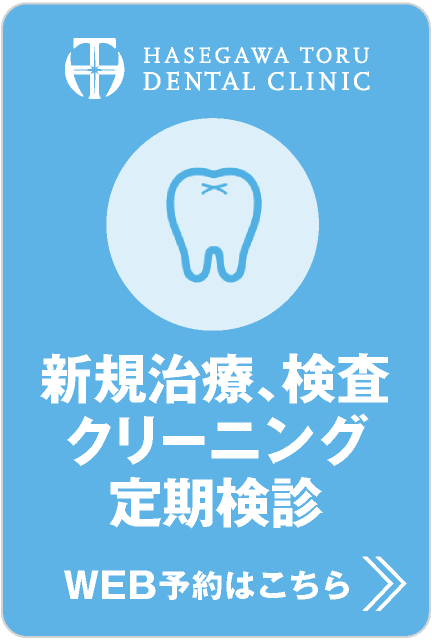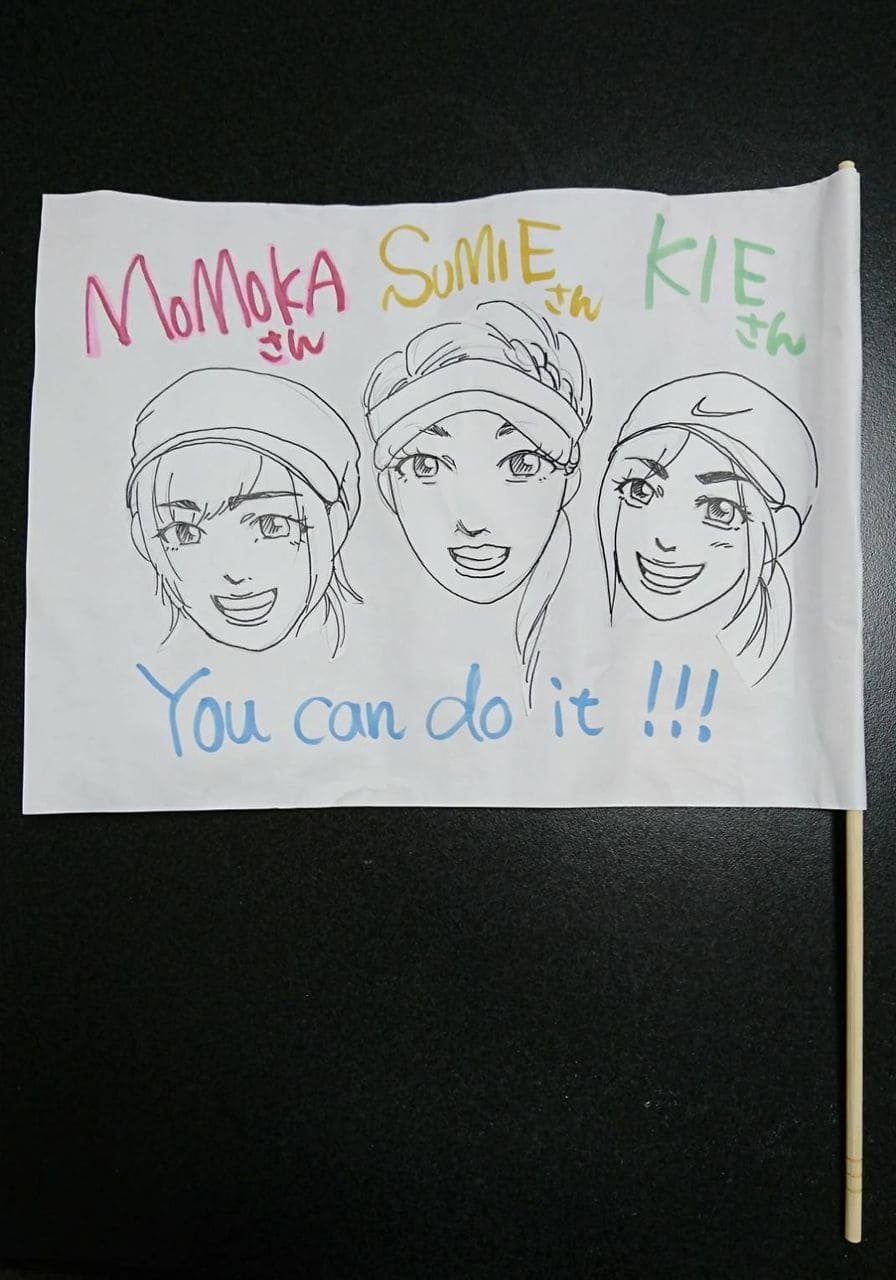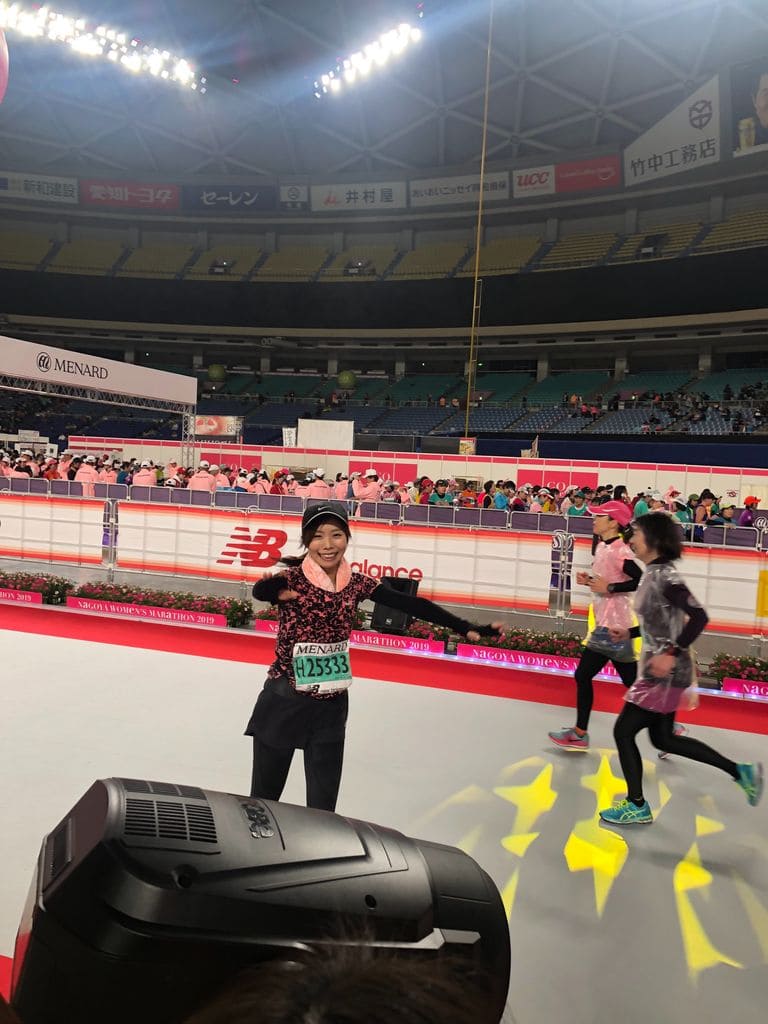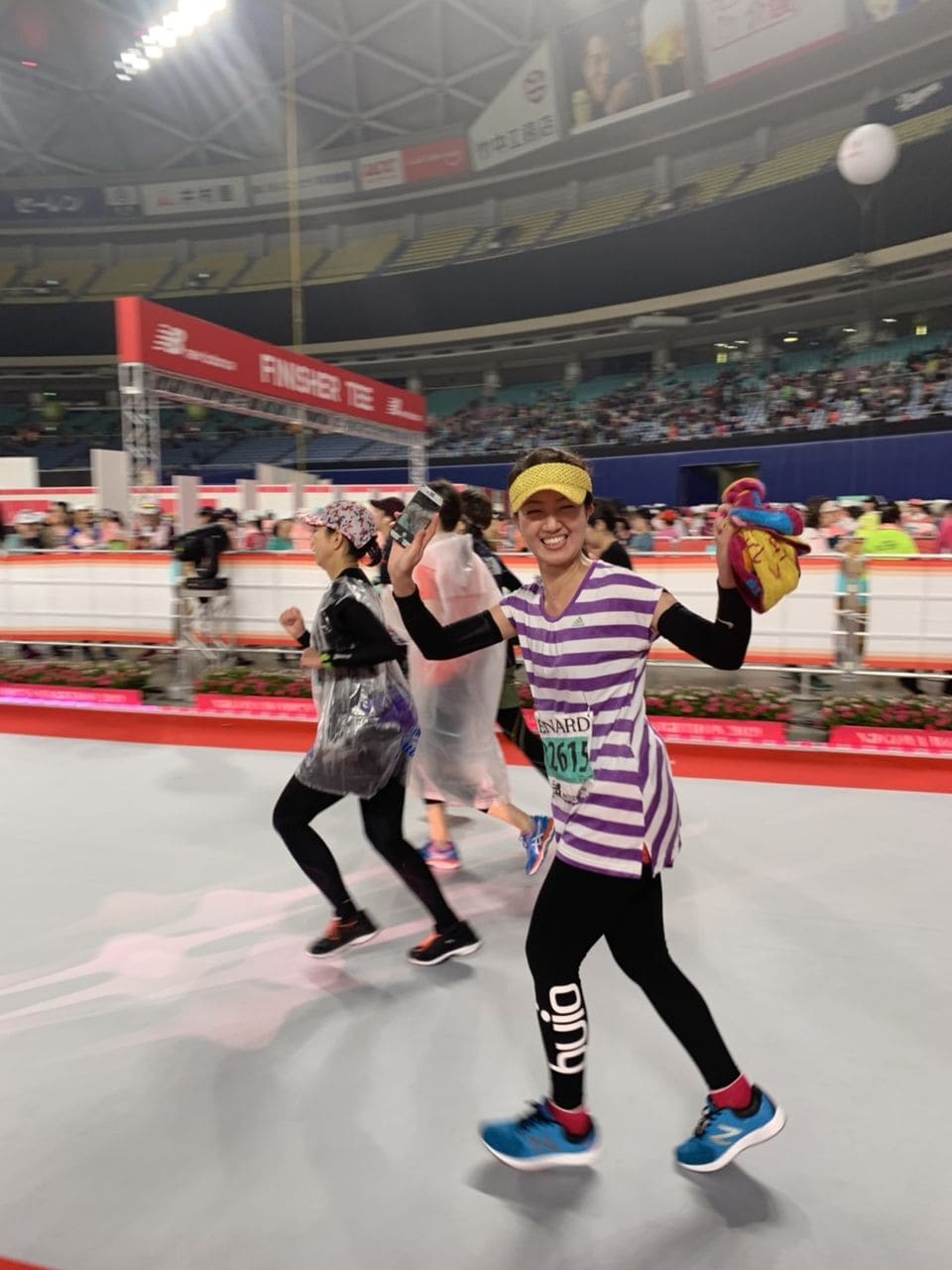皆様、こんにちは。
そしてはじめまして、昨今花粉症になってしまったかもしれない歯科助手のmanamiです。
この度、愛すべき同期のお二方がお誕生日を迎えましたので、私がブログ担当になりました。
今回院長先生に予約していただいたお店は、名古屋市新栄にあるイタリアンレストランのアンティカローマさんです。
(アンティカローマ写真)
(先に入店し、みんなを出迎えるmomokaさん)
今回は、木曜日のドクター宮地先生と吉成先生もご参加いただきました!
こんなセレブなイタリアンレストランは人生で初めてでした。。
お店の豪華さにも驚きましたが、
出迎えていただいたイケメンイタリアンボーイのニックさんの年齢に驚かされました!
なんと、私の3つ下の26才だそうです!ギャップ。。。
(ニックさん写真)
お店の雰囲気もスタッフも本場イタリアさながらのクォリティで (←私は行ったことないですが。)
さらに.ピアノの生演奏も聴かせていただき、大満足でした!!!
(ピアノの生演奏)
料理もほっぺたが落ちるほど美味しくて、ワインも沢山いただいてしまいました。誕生日でもないのに。。
院長先生、本当にいつもありがとうございます! 院長先生が飲んでいるワインはいつもとても美味しいです!
(料理の画像)
ピザの生地回し?を見たり、院長パワーで特別にお店のワインセラー見学など、
とても貴重な体験をさせていただきました!
目の前の光景の何もかもがオシャレすぎて震えました。。
是非皆様も大切な人とご一緒に足を運んでみて下さい。
そして今回の主役のyoshimoさんは22才になりました!
(yoshimoさん画像)
長谷川亨歯科クリニックで一番若い歯科衛生士さんですが、
しっかり者で22才とは思えないほどよく働きます!
たまに髪の色をピンクにしますが、中身はとても真面目です!←
そしてそしてもう1人の主役のyumikoさんは,
急なご事情で残念ながら不参加になってしましましたが、
後日、院長先生から可愛いバラの花束をいただいてとても喜んでいました!
(yumikoさん画像)
歯科助手のyumikoさんも22才になりました!
yumikoさんは意外と几帳面で丁寧な仕事っぷりにギャップを感じます!
たまにぶっ飛んだ発言をして皆んなを驚かせますが、本人は真面目に言ってます!
ハセシカの天然記念物アイドルです。
お肌も歯もキラッキラしてて眩しいです(泣)
私はいつも同期のお二人のお若い刺激をいただいているので、益々キラッキラして頑張ります!
yoshimoさんyumikoさんお誕生日おめでとうございました!
(集合写真)
少し長くなりましたが、ブログももう終盤です。
長谷川亨歯科クリニックは5月からリニューアルして以前の場所にお引越しとなります!
新しい医院となりスムーズにいかない事もあるかもしれませんが、
患者様一人一人が安心して通える医院を目指して引き続き勤めていきますので、
今後とも宜しくお願い致します。
今回のお店情報【アンティカローマ】
http://www.anticaroma.jp/