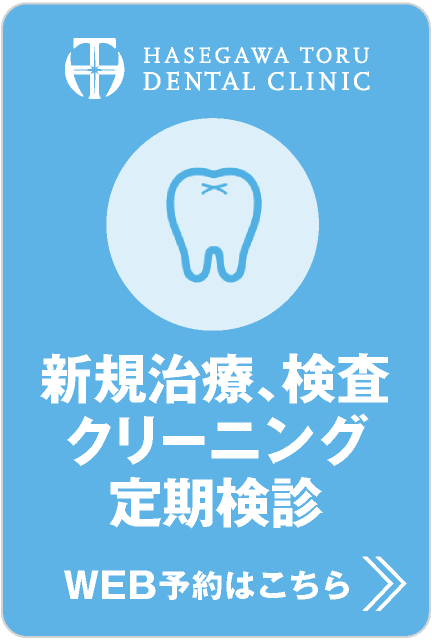10月29日、熊谷崇先生の講演会に参加しました。会場は東京・銀座のデンツプライシロナ株式会社ショールームでした。先生はご高齢のため、現在は一般向けの講演会を控えておられると伺っていましたが、東京勤務の知人からの情報で半年前に申し込み、このたび念願叶って受講することができました。
熊谷先生のご講演はこれまでにも何度か拝聴していますが、一般講演としては約10年ぶりでした。今回も2時間半にわたり休憩なしでお話しされ、その熱量とエネルギーは以前とまったく変わらず、深い感銘を受けました。

思えば私がまだ20代、開業前にアメリカの臨床現場を学ぼうとシアトル(ワシントン州)に約1か月滞在し、その後ペンシルベニア大学で研修を受けた頃のことです。すでに当時から熊谷先生は、独自の予防歯科医療の礎を築くため、アメリカや北欧の研究者たちと積極的に議論を交わしておられました。その情熱的な姿が今も印象に残っています。今回の講演でも、Edwin S. Rosenberg 博士(ペンシルベニア大学)、Roy C. Page 博士(ワシントン大学)、Per Axelsson 博士といった往年の名だたる研究者のお名前を懐かしく拝聴しました。
「名医とは、高度な治療技術を持つ歯科医ではなく、患者さんが治療を必要としないよう導ける歯科医である」――この言葉は、私が開業時に目指した理念と重なります。しかし実際にそれを形にするには、医学的な課題のみならず、社会制度的な障壁も数多く存在します。熊谷先生はそれら一つひとつに果敢に挑み、確実に成果を積み上げてこられた稀有な存在です。その歩みは、NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」や「カンブリア宮殿」「未来世紀ジパング」などでも紹介され、社会的にも大きな反響を呼びました。
名医の作った入れ歯で何でも噛めることは素晴らしいですが、自分の歯で噛める喜びには及びません。これは禅語にある「瘡(かさ)・疥(かいせん)を掻く快は、無病の安楽に及ばず(かゆい所を掻くと一時は快いが、“かゆみがない健やかな状態の安らかさ”の方が本質的に優れている)」という言葉を思い起こさせます。どれほど優れた入れ歯やインプラント治療であっても、生まれ持った健康な歯に勝るものはないのです。
この考え方は、埼玉県上尾市で開業されている飯塚哲夫先生の診療姿勢にも通じます。飯塚先生は、虫歯や歯周病を初期の段階で徹底的に治療し、再発を防ぐための口腔衛生管理を徹底されています。数十年にわたり近代口腔科学研究会を主宰し、歯科医療の本質を探求し続けておられる姿勢に、深く共感します。
酒田市における熊谷先生の50年に及ぶ取り組みはまさに驚異的です。2017年の公開資料によると、当時人口約10万5千人のうち約3割が受診し、1割以上が定期メインテナンスに通うとのことでした。さらに今回の講演では、酒田市民の約半数が日吉歯科を訪れているとのお話がありました。
同院の解析では、定期メインテナンスを受ける12歳児のカリエスフリー率が90%以上に達し、5歳から通う子どもでは20歳になっても約9割が虫歯ゼロとのことです。成人においても、長期メンテナンス継続者の75歳時点での平均残存歯数が18本(全国平均は約8本)という結果が示されています。
また、ボー・グラッセ先生(スウェーデン)が提唱した「メディカルトリートメントモデル(MTM)」を基に、検査値や画像をクラウドで患者と共有するシステムや治療プログラムの運用など、実際の診療の工夫についても多くの学びがありました。
最後に、テレビ番組「カンブリア宮殿」で村上龍氏が「良い予防歯科を見つけるには?」と尋ねた際、熊谷先生は次のように答えておられました。
「規格性のある写真、レントゲン、唾液検査、歯周病検査などを通じて、自分の口の中をきちんと理解できるようにしてくれる歯科医院なら、自分の口の“過去・現在・未来”を知ることができます。」
この言葉は、予防歯科医療の本質を的確に示しており、私自身の診療理念とも深く響き合うものでした。