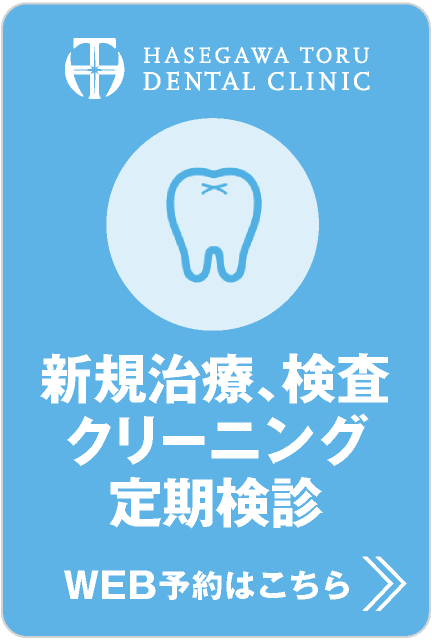当院の歯科衛生士 aikoさんが
患者さんの口腔内が変わる!
個別対応のセルフケア処方 即実践セミナー
の研修に参加しました。
毎週金曜日の歯科衛生士のミーティング(衛生士さんが自主的に行っている勉強会 )で
その報告を行うとのことで、今回は わたくし( 院長:長谷川 )も参加して聞いてみました。

歯や口のお掃除をすることを口腔清掃と言います。
口腔清掃には、歯ブラシ、歯磨き剤や洗口剤などを使用します。
口腔清掃のための器具や製剤は、数えきれないほどたくさんの商品が
世に出まわっていますが、その選択基準はかなり曖昧です。
テレビCMで見たり、知り合いに教えてもらったり、ドラッグストアーで手に取ってみたり・・・
何となく気に入ったものを使用しているのではないでしょうか。
内科医が患者さんの症状だけで無く、個々の体質や体調を考慮して、適切なお薬を処方するように、
歯科衛生士が、その星の数ほどある清掃器具や製剤(歯磨き粉なども含む)を、
それぞれの特性を理解し、患者さんに効果的に提供する技術がセルフケアー処方です。
セルフケアー処方が難しいのは、薬を飲むだけの処方と違って、
類似した症例に同じ処方をしても、同等の成果が得られるとは限らない点です。
つまり、同じ程度の虫歯になっている二人の患者さんでも、
それぞれの歯磨きの器用さや、実際のお手入れ状態、歯の質や食生活によって、
処方する歯ブラシ、歯磨き粉の種類は当然異なってきます。
また、現在治療中の患者さん用のケアグッズと、
メインテナンス(診療後の術後管理)中の患者さん用
では、やはり薦めるグッズは違ってきます。
ワンパターンが通用しないのがセルフケアーの難しいところです。
歯磨き剤や洗口剤では製剤の成分や、使用するケアーグッズの
それぞれの特性を理解した上で5つのターゲット(脱灰、歯質、歯石ステイン、細菌、炎症)
に対する基本方針を確認し、それぞれのターゲットに有効な成分や清掃法を選択して行く必要があり、
それは容易なことではありません。
数多くの製剤やケア-グッズの組み合わせの中から、症例経験を重ねていくことにより、
当院のオリジナルの処方パターンを作り上げ、効果的に患者さんに提供していきたいものです。
また、治療中における、歯面ケア、歯周ケア、そして治療ステージの
それぞれの処方ポイントをシステム化していければ、
効率的で効果的な口腔清掃を行えることと思います。
aikoさん、セミナーと報告お疲れ様でした。
とても有意義なセミナーであったと思います。