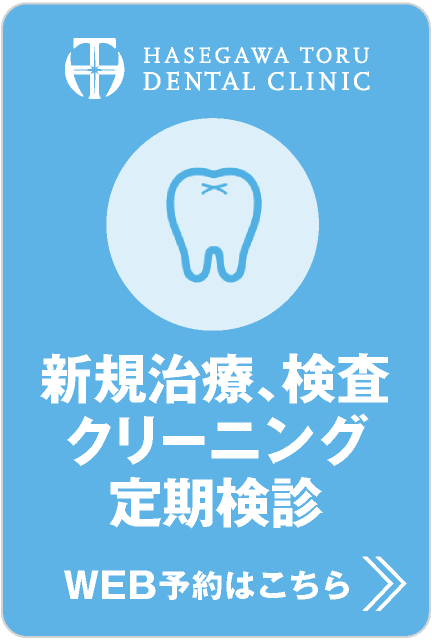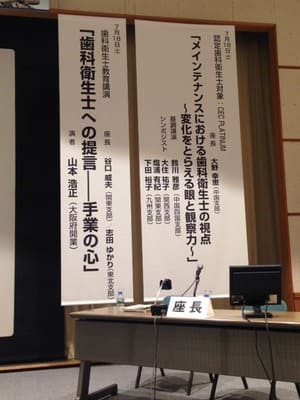新人歯科衛生士の和気です。私も、学会の報告をさせて頂きます。
学会当日の出発は朝早く、東京で新幹線を乗り継いで仙台へ到着です。
遠かったですが、初めての仙台にわくわくでした。
牛たん屋さんがいたるところに!
初ずんだもちもおいしかったです。
私は、今回が学会へ参加するのは初めてでした。
難しいお話もありましたがたくさんの衛生士さんのお話を聞き様々な症例を見ることができてとても勉強になったと思います。
もっとスキルアップしていきたいと思いました。
私は、毎日、お口のクリーニングをやっています。
クリーニングをやっていくときにそのお口だけを見て判断するのではなく
お口がある前にその人自身がいることを忘れてはいけないなと改めて気づきました。
その人の性格や生活背景なども考えて
患者さん1人1人にあった指導をやっていけるように
患者さんとのコミュニケーションを大切にしていきたいです。
伝え方にしても、危機感をあおるような伝え方ではなく また来たいな。と思っていただけるような患者さんのやる気を上げることができる話し方が大事です。
また、私が、聞きたいことを聞くだけでなく、患者さんの言いたいことを聞き出せるような言わせ上手になりたいです!!
今回の学会で感じたことを忘れず今後に生かしていけるよう頑張ります。
院長先生ありがとうございました。
和気