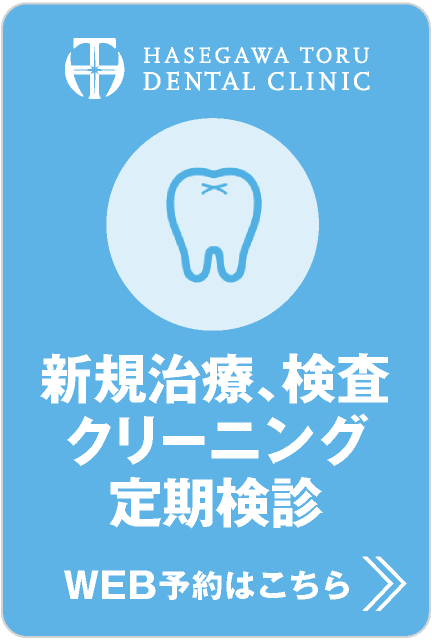11/22(土) JAO ( http://www.jaosseo.com/jao/ )の11月例会が行われました。
今回は 「近年の歯周病治療のトピックスー超高齢社会の歯周病治療を視野にー」 を演題に
松本歯科大学歯科保存学講座 吉成伸夫教授から、お話をいただきました。

歯周病予防には、プラークと呼ばれるお口の中の細菌を除去するための管理(ご自身の管理と歯科診療所での管理)が欠かせないのですが、75歳を境に、歯周病が一気に悪化する傾向があるとのことです。
8020達成者(80歳で20本の歯が残っている方 : 歯科医師会の運動が功を奏し近年増えてきています)
が、さらに高齢となってから、虫歯がひどく進行し大きな問題となるケースも多く報告されていますが、歯周病も同じ傾向が見られる事は、患者さんにとっても歯科医師にとっても 深刻な問題です。
虫歯も歯周病も、前述の通りお口の清掃、管理により予防されているので、それが十分に行われなくなると、やはり病気は進行してしまいます。
問題のなのは、ご本人がやる気があっても、手が自由に動かなくなったり、健康状態が悪化したりして、今まで通りのクリーニングを行えなくなってしまう点です。
吉成先生によると、パタカラ(口の周りの筋肉を鍛える装置)や音波ブラシによって唾液の量を増加させ、歯周病進行抑制の一助としているとか。
今後ともさらに、歯科医師からの積極的な関わりが求められると思います。
さて、例会後は懇親会があります。
今回は、富田林市から加藤先生ご夫妻、山梨から秋山先生がご参加され、楽しく親交を深めることができました。

ちなみにお店は
「旬処 魚こう 」 でした。
050-5890-5101 (予約専用番号)
住所 愛知県名古屋市東区東桜1-2-4