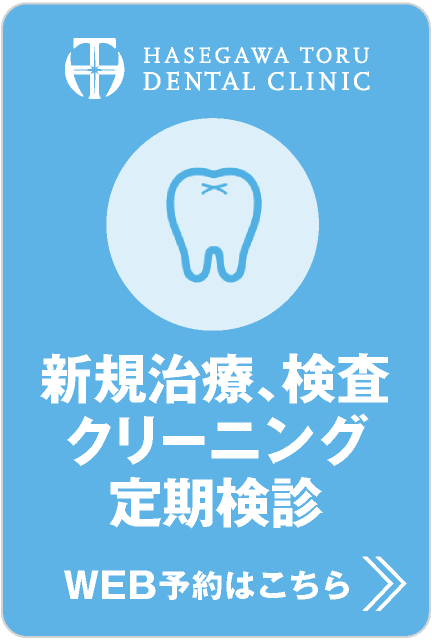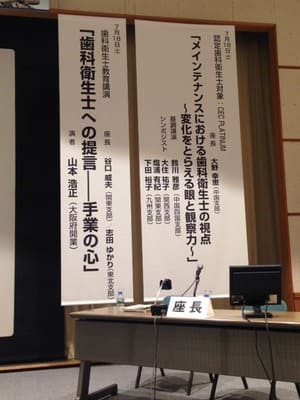7月9日(土)10(日)の二日間、アクロス福岡(福岡市)に於いて日本臨床歯周病学会 第34回年次大会が開催されました。
本年のテーマは「歯周治療 成功の鍵 再生療法 Step by Step」です。
当クリニックでは今年も、歯科衛生士5名と共に参加しました。
※ 2日目の3人の先生によるディスカッション
再生療法は、この数年主題となっているテーマです。
再生療法は一言でいえば、
「一度歯周病で失われた歯周組織を再生する療法」 です。
歯周病の進行により、歯周組織(歯を支えている歯根膜や歯槽骨 等)が破壊されますが、
一度破壊された歯周組織は自然には元の状態へ戻ることはありません。
歯周病治療では、ご家庭での口腔清掃や、診療所での歯石除去やクリーニングで、
歯の周囲の細菌を徹底的に除去することにより、抜歯を避けるよう試みるのですが、
炎症は治まっても、破壊された歯周組織はそのままです。
そこで、破壊された組織を積極的に増やす治療法が再生療法です。
具体的な治療法としては、このブログでも以前紹介させていただいた、
EMD (エムドゲイン) やGTR (人工膜を利用して骨を誘導する方法) がメインですが、
残念ながら十分普及しているとは言い難い現状です。
その理由として、再生療法を進めるに当たり前提となるのが
① 歯科医が歯周病の基本手技を的確に行うことができること
② 患者さんに、その効果についてご理解していただけること
ですが、この両方を満たすことが簡単そうで難しいからです。
歯科大学の教育課程では歯周病治療の手技の詳細を学ぶところまでカバーされていませんし、
歯周病の進行や治癒は、細やかな症状の変化やレントゲン所見から判断されるので、
患者さんにそれを理解していただくには、治療者側の懇切丁寧な説明と受診者側の協力と闘病意欲が必要です。
「ぐらぐらで抜けそうな歯が、エムドゲインをつけたら一発でしっかりした」というような効果があればよいのですが、なかなかそういう訳にはいかないのです。
今回のテーマは、そのような普及しにくい再生療法が少しずつ(Step by Step)理解され実用化される目的でプログラムが組まれていました。
話が堅くなってしまいましたが、福岡と言えば”もつ鍋”です。
その様子も含め、あとは一緒に参加した歯科衛生士の皆さんの報告をご覧ください。