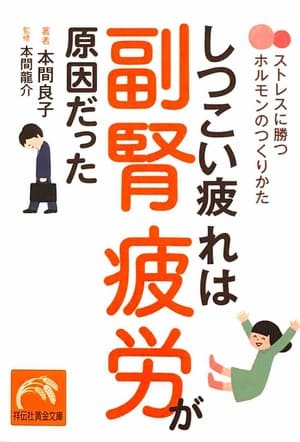当クリニックでは、在宅診療はあまり積極的に行っておりませんが、その意義と重要性をについて考えさせられる研修会でした。
研修会・講習会
愛知学院大学歯学部三谷教授の学術講演 ~ 公式ブログより
公式ブログ更新 EBAC(口臭治療)合同研修会
JAO定例研修会(経皮的曝露について)
2019年9月28日
JAO(日本オッセオインテグレーションアカデミー)の9月定例研修会が開催されました。
講師は国立病院機構名古屋医療センター 歯科口腔外科医長の宇佐美 雄司 先生でした。
テーマは
「歯科診療における経皮的曝露(針刺し)の対応」
と
すこし難解な題目ですが、
いわゆる医療従事者の針刺し事故に対する対処法についての講義でした。
すこし難解な題目ですが、
いわゆる医療従事者の針刺し事故に対する対処法についての講義でした。
名古屋医療センターは今回のような医療事故に対する感染のみならず、
東海ブロックの、医療感染に対する拠点としての機能を果たしています
当院でも対策を行っていますが、
針刺し事故は、各自が注意するというよりも、
事故が起こらない仕組み(システム)が大切であると思います。
一旦事故が起こると、まず検査を行いますが、
これは免疫を有しているかどうかのの検査であり、 針刺しにより感染したかどうかがわかるのは約1ヶ月後であるとのことです。
そしてその後も3から6ヶ月毎にフォローが必要です結論としては、最も感染の可能性が高いB型肝炎(HBV)への対策として
ワクチン接種を受けることが最も有効な針刺し事故対策であるとのお話でした。
ワクチン接種を受けることが最も有効な針刺し事故対策であるとのお話でした。
副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)についての セミナー
9月26日、副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)についての セミナーに参加しました。
講師は名古屋市千種区のアルゴメディカルサロン院長小倉行雄先生(医師 )です。
副腎は、左右の腎臓の上部にあるホルモン分泌器官で、
ストレスに対処するホルモン「コルチゾール」をはじめ、
生命の維持に欠かせない様々なホルモンを分泌する器官ですが、
ストレスによりコルチゾールが過剰に分泌される状態が続くと、
副腎が疲れて必要なときに十分な量を分泌できなくなり、
ストレスと闘えなくなる。
この状態を『副腎疲労(アドレナル・ファティーグ)』と呼ぶそうです。
正式な病名ではなく、欧米や日本のような先進国でもまだ深く認知されていない病気ですが、
副腎疲労になると、炎症を抑えられず
疲労感や様々な不調が出やすくなると言われています。
例えば、副腎から分泌されるコルチゾールは血糖値や血圧のコントロール、
免疫機能や神経系のサポートをつかさどるため、
副腎疲労を起こして分泌がうまくいかなくなると、
生活習慣病やうつ症状、花粉症などのアレルギー症状、
橋本病やバセドウ病などの自己免疫疾患を発症することもあるとの事です。
ここでいうストレスには、精神的なストレスだけでなく、
大気汚染や食品の添加物、気温の変化、食生活の変化、
持病や感染症など、体内で炎症を起こす恐れのあるもの全てが含まれ、
歯科で使用されるかぶせものや詰めものの金属が、
副腎の機能と関連するとのことです。
歯やお口に問題が無いのに、不定愁訴を訴えられる患者さまへの
対処法の1つとして考えたいと思います。
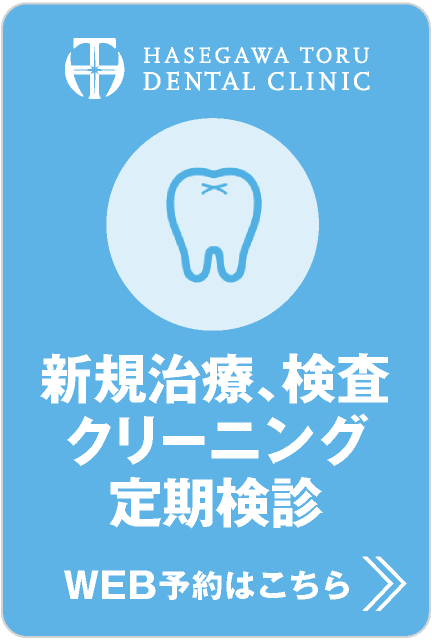


 こちらからどうぞ
こちらからどうぞ 12月27日に更新しました。
12月27日に更新しました。